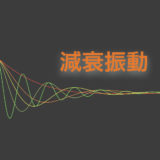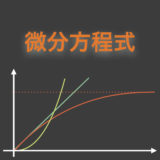重力だけが物体に働いて落下する「自由落下」と、速度に比例する抵抗「粘性抵抗」が作用しながら落下する運動を扱います。
微分方程式の解き方も丁寧に説明します。まずは素朴に、運動方程式を眺めて解を考えてみたり、変数分離という手法を使ってみたり、解の大体の形を知っていれば微分するだけで解を求められたり…と色々と導出してみました。好きな方法・自分に合った方法で練習すると身につくと思います。
指数関数の微分方程式にまだ慣れてない方はこちらもどうぞ↓
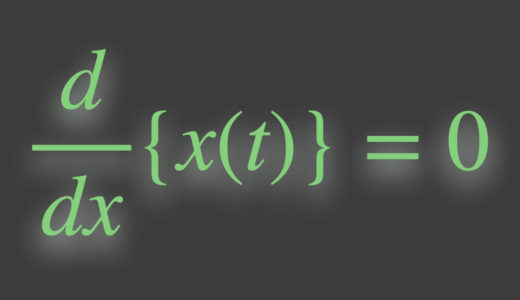 初めての微分方程式
初めての微分方程式
慣性抵抗の記事も書きました↓
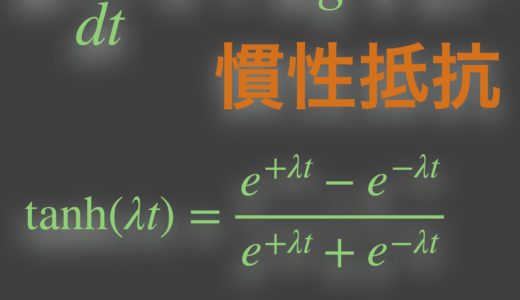 慣性抵抗の問題を解いてみる
慣性抵抗の問題を解いてみる
目次
抵抗がない場合の自由落下
まずは物体に抵抗が働かない場合について考えてみましょう。運動方向$y$の座標軸を、下向きに取った場合には、この座標軸の向きに重力$mg$が働くため、力の値は正となることに注意して、運動方程式は、$\frac{dy}{dt}=v$として、$$m\frac{dv}{dt}=mg$$と書けます。一方、座標軸を上向きに取った場合には、座標軸と逆の向きに重力が働くため、力の値は負になるように、$$m\frac{dv}{dt}=-mg$$となります。これ以降は1つ目の、座標軸を下向きに取った場合の運動方程式について考えていきます。
運動の追跡の目的は、速度や位置の関数$v(t), y(t)$を知ることにあります。まずは、速度がどのように時間変化するのかを考えてみます。
$$f^{\prime}(t)>0\Rightarrow{}f(t+\Delta{t})>f(t)$$であり、微分係数が正のとき、関数$f(t)$は増加します。ここで、$f(t)=mv(t)$とおけば、それは運動量であり、その時間的な変化は力$f$によって決まるというのが運動方程式の意味しているところです。
素直に解を求めてみる
先程の運動方程式の両辺を質量$m$で割ると、$$\frac{dv}{dt}=g\ (>0)$$となります。この式を読めば、速度の変化率を表す$\frac{dv}{dt}$が常に正の値を取ることがわかるので、時間が経てば経つほど物体の速さは大きくなることがわかります。では、具体的にどんな感じで速くなっていくのか知りたければ、両辺を時間$t$で積分すればよく、$$v(t)=gt+C_1$$と計算できて、速度の速くなり度合いは1次関数であることがわかります。ここで$C_1$は積分定数(任意定数)で、この値は初期条件で決まります。もう1回時間$t$で積分すれば、$$y(t)=\frac{1}{2}gt^2+C_1t+C_2$$と計算できて、位置の関数も求めることができました。これはそこまで難しい積分ではないですが、一応チェックとして、$y(t)$を時間$t$で微分したら速度$v(t)$になり、それをさらに時間$t$で微分したら加速度$\frac{dv}{dt}$になることを調べておくと検算ができます。
解を知ってる人はサッと解ける
速度や位置の関数はめでたく求めることができたわけですが、既に関数の大体の形を知っていたら微分だけで解くことができます。位置の関数が2次関数であることを知っていれば、解の形を、$$y(t)=a_0+a_1t+a_2t^2$$と仮定することができます。これを2回微分して運動方程式と見比べると、$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}=2a_2=g\ \therefore{a_2}=\frac{g}{2}$$のように2次の係数が求まり、残りの定数は初期条件で決まります。例えば、$t=0$で$v(0)=v_0, y(0)=y_0$だとすれば、解は$$y(t)=y_0+v_0t+\frac{g}{2}t^2$$となります。このように解の形に見当が付けば、代入するだけで解けてしまいます。これは、線形微分方程式で、解を$e^{\alpha{t}}$と決めつけて代入して$\alpha$を求めるのと似ています。
粘性抵抗が働く物体の落下
次に、落下する物体に粘性抵抗(速度に比例する抵抗力)が働く場合を考えてみます。運動方向$y$の座標軸を、下向きに取るなら運動方程式は$$m\frac{dv}{dt}=mg-\lambda{v}$$となります。抵抗力は、運動を妨げる向きに働きます。すなわち、速度$v$を変化しないような、$\frac{dv}{dt}=0$へ近づくような向きに働きます。
素直に解を求めてみる
この運動方程式の両辺を質量$m$で割ると、$$\frac{dv}{dt}=g-\frac{\lambda}{m}{v}$$となります。自由落下の場合と同じように、速度$v$の時間変化を考えてみます。速度$v$がどんな値の時に速度は増加し($\frac{dv}{dt}>0$)、どんな値の時に減少し($\frac{dv}{dt}<0$)、どんな値の時に定常状態になる($\frac{dv}{dt}=0$)のかを調べるわけです。それは、この式の右辺の符号で決まりますが、このままだと一瞬で符号を判別するのは難しいので変形していきます。
先程の微分方程式を変数$v$の係数$-\lambda/m$で括ると、$$\frac{dv}{dt}=-\frac{\lambda}{m}\bigg(v-\frac{mg}{\lambda}\bigg)$$となります。$\dfrac{dv}{dt}=0$となる速度を$v=\dfrac{mg}{\lambda}$を $v_{\infty}$ とおけば、$$\frac{dv}{dt}=-\frac{\lambda}{m}\textcolor{red}{(v-v_{\infty})}$$となります。ここまで変形すれば、今の速度$v$と$v_{\infty}$の比較で微分係数が決まることが明らかになります。結局、$v(t)$の時間変化の鍵を握るのは、変数$v(t)$そのものよりも、$\textcolor{red}{(v-v_{\infty})}$という固まりであることがわかります。
ところで、定数は微分したら消えるので、この微分方程式の左辺にも$\textcolor{red}{(v-v_{\infty})}$という固まりを作ることができます。$$\frac{d\textcolor{red}{(v-v_{\infty})}}{dt}=-\frac{\lambda}{m}\textcolor{red}{(v-v_{\infty})}$$左辺の計算を実行すれば、$\frac{d(v_{\infty})}{dt}=0$より1つ上の微分方程式に戻すことができます。この形を見たら、指数関数の微分法:$$\frac{d(\textcolor{red}{e^{\alpha{t}}})}{dt}=\alpha{\textcolor{red}{e^{\alpha{t}}}}$$が想起されます。固まり$\textcolor{red}{(v-v_{\infty})}$と、指数関数$\textcolor{red}{e^{\alpha{t}}}$が相似の関係にあるので、結局、$$(v-v_{\infty})=C_1e^{-\frac{\lambda}{m}t}\ \ \therefore{v}=v_{\infty}+C_1e^{-\frac{\lambda}{m}t}$$と解が求まりました。
初期条件($t=0$)を$v(0)=v_0$とすれば、$$v(t)=v_{\infty}+({v_0-v_{\infty}})e^{-\frac{\lambda}{m}t}$$となります。この解は、時間が十分に経ったら収束する「終端値の$v_{\infty}$」に、「どんどん減少していく初速度と終端値の差$({v_0-v_{\infty}})e^{-\frac{\lambda}{m}t}$」が重ねられた式と言えます。
よくやる変数分離という手法で解を求める
微分方程式を解くときによくやるテクニックの1つに「変数分離法」というものがあります。こちらの方がより広い範囲に使える方法なので、この方法でも解いてみます。具体的には、$\frac{dv}{dt}$のような微分の項が左辺に入っている式の、右辺をこの$v$と$t$それぞれの関数$V(t), T(t)$の積で表すと解けるようになる、という手法です。式で見てみましょう。運動方程式の両辺を質量$m$で割った式: $$\frac{dv}{dt}=g-\frac{\lambda}{m}v$$の右辺を$v$の関数$V(v)$と、$t$の関数$T(t)$の積で表すわけです。この微分方程式が、$$\frac{dv}{dt}=V(t)\cdot{T(t)}$$と書けた場合、$$\frac{dv}{V(v)}=T(t)dt$$と変数を両辺で分離することができて、これを積分すれば解が求まります。今は、$$V(v)=g-\frac{\lambda}{m}v,\ \ T(t)=1$$と置けば、$$\frac{dv}{g-\frac{\lambda}{m}v}=dt$$と変数を分離することができて、両辺を積分すると、$$\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{g-\frac{\lambda}{m}v}=\int_0^{t}dt$$より、$$-\frac{m}{\lambda}\bigg\{\ln|g-\frac{\lambda}{m}v|-\ln|g-\frac{\lambda}{m}v_0|\bigg\}=t$$整理すると、$$\ln\bigg|\frac{g-\frac{\lambda}{m}v}{g-\frac{\lambda}{m}v_0}\bigg|=-\frac{\lambda}{m}t$$ここで、初速度$v_0$は終端値$v_{\infty}=\frac{mg}{\lambda}$よりも小さい正の値とすれば、速度は$0\leq{v(t)}\leq{v_{\infty}}$であるため、絶対値記号の中身は正の値になります。絶対値の中身の分子分母に$(-\frac{m}{\lambda})$をかけて整理すると、$$\ln\bigg(\frac{v-\frac{mg}{\lambda}}{v_0-\frac{mg}{\lambda}}\bigg)=-\frac{\lambda}{m}t$$両辺の指数関数を取れば、$$v-\frac{mg}{\lambda}=\bigg(v_0-\frac{mg}{\lambda}\bigg)e^{-\frac{\lambda}{m}t}$$より、$$v(t)=\frac{mg}{\lambda}+\bigg(v_0-\frac{mg}{\lambda}\bigg)e^{-\frac{\lambda}{m}t}$$先ほどと同じ式を得ることができました。
非同次の微分方程式という見方
今回の微分方程式は、$$\frac{dv}{dt}+\frac{\lambda}{m}v=g$$という形ですが、これは微分方程式の分類で「非同次」というものになります。ここで、右辺が$0$となる場合を「同次」の微分方程式といい、$$\frac{dv}{dt}+\frac{\lambda}{m}v=0$$こちらは簡単な指数関数の形になっているのですぐに解くことができます。$$v(t)=C_1e^{-\frac{\lambda}{m}t}$$一方の右辺が$0$でない「非同次」の場合、一般に右辺に指数関数や三角関数が来たりと、いきなり解くのが大変になったりします。でも今回は右辺が定数の一番優しい場合で、右辺が$0$になるように変形してしまえば解けてしまいます。具体的には、変数を$$v(t)=v^{*}(t)+C$$のように定数だけずらすような変換を行います。定数だけずらすので、微分のところには影響が及ばず、式の形をできるだけ保って変形することができます。実際に代入すると、$$\frac{d(v^{*}(t)+C)}{dt}+\frac{\lambda}{m}\{v^{*}(t)+C\}=g$$より、$$\frac{\lambda}{m}C=g$$となるように定数$C$をとれば「同次」に持ち込めて、$$\frac{d(v^{*}(t))}{dt}+\frac{\lambda}{m}v^{*}(t)=0\ \ \therefore{v^{*}(t)=C_1e^{-\frac{\lambda}{m}t}}$$変数を$v^{*}(t)=v(t)-C$で戻せば晴れて解き終わることになります。